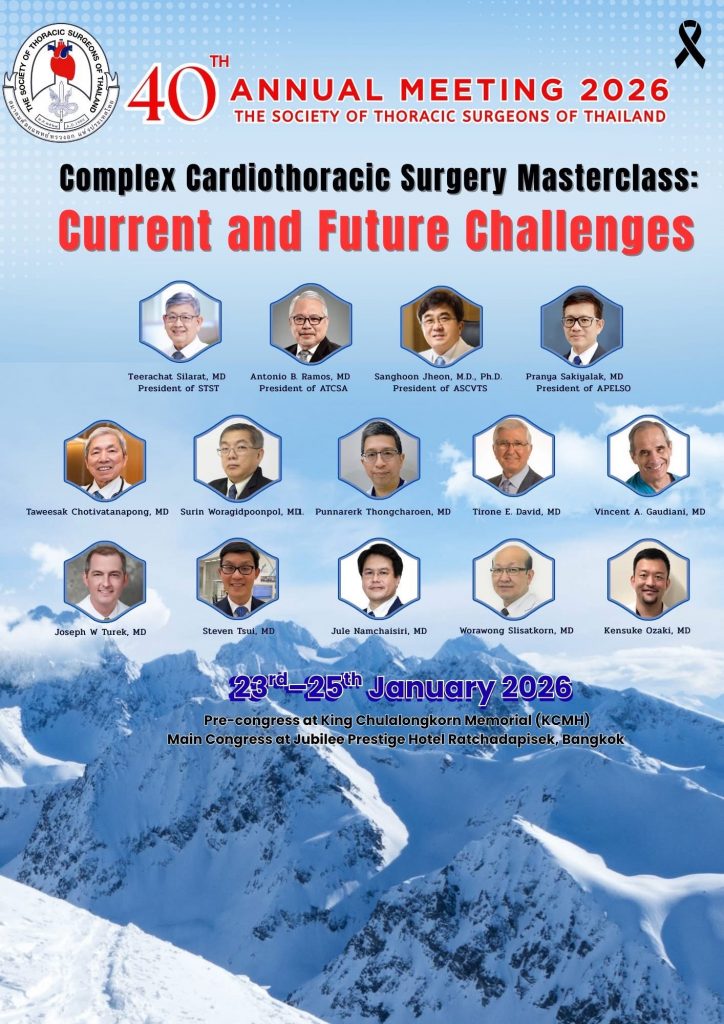川崎大動脈センター(KAC)と台湾血管外科学会(TSVS)の間で、協力覚書(MOU)の調印式が執り行われました。本式典は、両組織の長年にわたる交流を祝すとともに、学会規模での新たなパートナーシップを確立するものです。
プレゼンテーションでは、KACの基本理念や豊富な手術実績、世界トップレベルの治療成績、そして国際協力への取り組みが紹介されました。両組織のリーダーは互いに敬意を表し、教育的交流や共同研究、長期的な協力体制を通じて大動脈外科を発展させていくという共通のビジョンを掲げました。
Ceremony marks the formal signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the Kawasaki Aortic Center (KAC) and the Taiwan Society for Vascular Surgery (TSVS). The event celebrated a long-standing relationship and established a new, society-wide partnership. Presentations highlighted KAC’s guiding philosophy, extensive surgical history, world-class outcomes, and commitment to international collaboration. Leaders from both organizations expressed mutual respect and outlined a shared vision for advancing aortic surgery through educational exchange, joint research, and long-term cooperation.